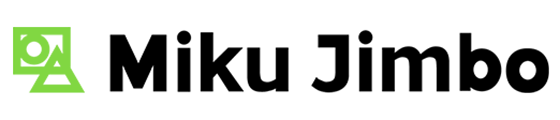写真と絵画の親密な関係;ロンドン展の覚書
幸か不幸か、先月はブログを書く余裕がありませんでした。
仕事が忙しいという意味では「幸」。このご時世に仕事をいただけるのは本当にありがたいことです。
ただ、フリーライターとは仕事に励むほどパソコンに向き合う時間が増える難儀な職業で、襲いかかるのは激しい肩こりと頭痛。頭が割れんばかりの痛みのせいで、仕事以外の時間はパソコンから離れて体を休めていました。
幸せとは、一筋縄ではいかないものです(治療の甲斐あり現在は元気です)。
そういった事情もあり、先月は、仕事以外の時間は写真集を見たり西洋絵画史を学んでいました。
西洋絵画の面白さがわかり始めたのは最近のことで、美術館で絵を楽しめるくらいの基礎知識は欲しいなと思い勉強中です。
そして先日、《ロンドン・ナショナル・ギャラリー展》に行きました。
普段はロンドンのナショナル・ギャラリーに展示されている61作品が日本に集っています。こういった展覧会は初めての試みとのこと。
感染症予防のため、この展覧会は事前予約制。
入場待ちで並ぶ必要もなく、人気作品も近くでじっくり見られます。

フォトスポットでさえ誰もおらず、写真が撮り放題…。
にわか知識でロンドン展や作品について語ってもアラが出るので(苦笑)、今回は主観てんこもりで感想を述べたいと思います。
そもそも西洋絵画を勉強しようと思ったきっかけは、写真上達のヒントを得たかったからです。
「よい写真とは何か」が自分の中で定まらなくなってしまい、いわばスランプ状態に。いろんな写真を見ても答えが出なかったため、絵画にヒントをもらおうと考えました。
写真と絵画の関係については意見が分かれるところで、「どちらが優れた芸術か」という議論は古くから繰り広げられています。
ただ、個人的には優劣はないという考えです。
著名な画家たちがカメラの技術を借りて絵を描き、多くの写真家が絵画の構図を模倣したように、写真と絵画は刺激し合う関係にあると考えています。
例えば、今回のロンドン展にも作品が展示されているフェルメール。
彼は「カメラ・オブスクラ」という原始的なカメラを絵画の制作に使ったといわれています。
そのためフェルメールの絵はどこか写真らしさがあります。時間の流れの中から一瞬を切り取ったような、思わず絵に見入ってしまう静けさ。光と影の描き方も巧みで、謎めいているけれど、温かさも感じられます。
同時期のオランダで、「光と影の魔術師」と呼ばれたレンブラントという画家もいます。
明暗がはっきりしたダイナミックな表現が特長で、ロンドン展で彼の自画像を見たときには息を飲みました。
彼の画風を写真撮影に応用した「レンブラント・ライティング」というライティング方法もあるくらい、レンブラントの絵は写真と親和性が高いです。
フェルメールとレンブラントの絵から感じたのは、影を意識することの重要性です。
写真を撮る上で「光を意識するように」とはよく言われますが、影があるからこそ引き立つものがあるのだなと、作品を通して理解できました。
そこで、自分が写真を撮るときにも影を意識するように。

全体が明るくなるように撮るより、影をとらえたほうが印象的な写真になりました。
影を意識することの大切さを教えてくれた巨匠2人の絵を、今回生で見ることができて嬉しかったです。
ロンドン展をきっかけに知ったゲインズバラという画家の「シドンズ夫人」という絵にも、写真に近いものを感じました。
この絵は夫人の顔の描写が緻密なのに対し、手などのほかの部分の描写は淡くなっていて、鑑賞者の目線を誘導するようになっています。
写真でも、一部分にピントを当ててほかの部分をボカすというテクニックがありますが、それに通ずるアプローチだなと思いました。

実際の絵の画像が載せられないので、過去に自分が撮った写真をイメージ画像として掲載…。
ロンドン展で楽しみにしていた絵のひとつが、モネ「睡蓮」です。
遠目で見ると幻想的なのに、近くで見ると迫力があって…長い時間眺めてしまいました。
印象派の代表画家であるモネは、自然を通して自分の感覚を表現した画家と言われています。
また、光や季節の変化を捉えるために何度も同じ風景を描いたというエピソードも有名。「睡蓮」シリーズは200本以上描いたとか。
その「継続は力なり」的な根気強さに胸を打たれて、私も自宅の同じ場所で何枚か写真を撮ってみました。5枚くらいですが。
すると、ある日の夕方。植物の影が美しく浮き出てきた瞬間に出会うことができました。

あえてピンボケで撮ってみました。
なお、ロンドン展にはベネチアやローマの絵が多数飾られていました。
自分が実際に見た風景と同じものが名画に描かれていると、ものすごく感動します。
何百年も前の世界と現在が繋がっていることを感じられる、遺跡を見たときと同じような類の高揚感。
「世界はそれをロマンと呼ぶんだぜ」。

イタリア旅行の際に自分で撮った写真。ロンドン展には、これらの建造物が描かれた絵もありました。
「いい写真とは何か」を考えるにあたって、写真論の古典といわれる本を何冊か読みました。
その中で、ロラン・バルトという批評家・思想家・学者による『明るい部屋―写真についての覚書』という本と出会ったのですが、彼の分析がとても印象的でした。
バルトは、写真を見るときの関心・感情の要素を「ストゥディウム(studium)」と「プンクトゥム(punctum)」という概念で論じています。
「ストゥディウム」は、”好き””素敵”といった当たり障りのない一般的関心。教養を通じて感じられるものです。対して「プンクトゥム」はストゥディウムを破壊・分断するもので、大抵の場合は写真の細部にあらわれます。
本を読んだときは、この分析の意味がイマイチつかみきれませんでしたが、今回のロンドン展でゴッホの「ひまわり」を見て、バルトの言いたかったことが少しわかったような気がしました。
「ひまわり」は、ゴーギャンという画家と共同生活するためにゴッホが描いた7枚の連作です。そしてロンドン展で展示された「ひまわり」は、ゴーギャンが絶賛した4番目に描かれた作品。
そんな4枚目「ひまわり」を遠目から見たときの第一印象は「わぁ、素敵だなぁ!」「やっぱりゴーギャンが絶賛しただけあるな」でした。
そして、いざ近づいて絵を見てみると、わたしは左下に描かれた首を垂れたヒマワリに目を奪われました。
言葉では伝えにくいのですが、その左下のヒマワリの質感、絵具の盛り具合が愛おしく感じたのです。
長いあいだ左下のヒマワリを見つめていたので、端から見たら怪しかったと思います。
遠目から見たときの”素敵”という当たり障りない感情や、ゴーギャンが絶賛したという知識を踏まえた上での「やっぱりゴーギャンが~」といった感想は、ストゥディウムに当てはまると思います。
一方でプンクトゥムは「左下のヒマワリの質感」です。
写真においても、主題をいかに切り取るかがまず大切ですが、ときに思わぬ細部が人の心を動かすことがあり得る。だからどうというわけではないのですが、写真を撮る上でこのことは心に留めておかなければと思いました。
なお、ゴッホの「ひまわり」は本当に素ン晴らしい絵で、絵を見てあれほど感動したのは、ムンク「太陽」以来でした。「ひまわり」を見るためだけに、もう一度ロンドン展に行きたいくらい。
ロンドン展は有名な絵も多く、薄っぺらい知識でも十分楽しめました。東京は10月18日まで開催しているので、少しでも興味がある方はぜひ足を運んでみてください。2020年11月~2021年1月は大阪にて開催されます。
ということで、今回は写真を絡めながらロンドン展の感想を述べました。
決して、著作権の都合で絵画の画像が載せられないからこのような形式にした訳ではありません。決して。
果たして、絵画から吸収したものを自分の写真に昇華できるのか……今後にご期待ください。
今回の一枚は、ゴッホにちなんでヒマワリの写真です。